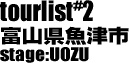富山県東部に位置する魚津市は古くから漁業・商業の街として栄えてきました。魚の種類が多く、県下屈指の漁場でもあります。西は日本海富山湾に面し、東には僧ヶ岳、毛勝山、剣岳などの北アルプスの山々が広がります。「蜃気楼」が出現する街であり、3月下旬から6月上旬にかけての暖かな日中の富山湾上に、森や橋、煙突の様な景色を様々に変化させて現れます。同じ時期、夜になると今度はホタルイカが青紫色の光を放ちながら魚津沖に産卵のために集まります。また、縄文時代末期の原生林が沈降してできた埋没林が、海中から発見されたときのまま保存されています。
データ:(2002.3月現在)
登録人口 47,138人(男22,666人 女24,472人)
世帯数 14,877世帯
消費者物価指数 2000年12月 101.3
<気候>
対馬海流による海洋性気候。北陸特有の多雨多湿型。冬期は多量の積雪地帯。
年平均気温 約13℃(東京 約16℃)
8月平均気温 26.8℃
1月平均気温 2.1℃
年間降水量 約2736mm(日本平均約1750mm)
積雪最高値 54cm(1月)
<姉妹都市>
姉妹都市 岡山県井原市・タイ王国チェンマイ市
地名の由来:
旧来、「魚堵」として、小戸ケ浦・小戸・小津と呼ばれてきたが、魚の産地ということから魚津に改称したとされている。
◎車で
東京から 関越自動車道、北陸自動車道 約5時間10分
大阪から 名神高速道、北陸自動車道 約4時間20分
名古屋から 東名・名神高速道、北陸自動車道 約3時間30分
◎電車で
東京から 新幹線利用で 約3時間10分
大阪から 特急利用で 約3時間40分
名古屋から 特急利用で約3時間40分 富山乗り換えで40分
◎飛行機で(富山空港着)
名古屋から 2時間
東京から 2時間
北海道から 2時間35分
福岡から 2時間35分
歴史的スポット
松倉城跡 など
みどころ
魚津水族館、ミラージュランド、埋没林博物館、歴史民俗博物館など
自然・温泉
蜃気楼、埋没林、ホタルイカ、名水
イベント
しんきろうマラソン、戦国のろし祭り、魚津まつり、たてもん祭り など
特産品
・ホタルイカ
シーズンは4月上旬~5月中旬。7cmほどのちいさな発光イカで、産卵のため、夜間の浅瀬に押し寄せます。とれたてをすぐに茹でた桜煮を辛子酢味噌で。刺身も産地ならでは。お土産には塩辛も。
・鰤(ぶり)
日本海の冬の味覚といえばこれ。日本海の荒波に揉まれた天然物でしか味わえない刺身を是非。照り焼き、かまの塩焼き、ブリ大根などおなじみの料理もひと味違います。
・りんご(ふじ)
魚津のリンゴは「加積りんご」と呼ばれ親しまれています。
リンゴ生産地としては比較的南に位置し、結果、十分な糖度になったところで収穫できるため、甘さたっぷり。独特のミツが入った全国屈指の味です。
・かまぼこ
富山県の結婚式に欠かせない細工かまぼこ。白身のかまぼこに、あわび、さより、甘エビなどをのせた「鮨蒲」は人気商品です。

魚津駅の名水
|

魚津漁港
|
BACKGROUND OF MIRAGE OF BLAZE
~「炎の蜃気楼」に登場する風景~

しんきろうロード
|
しんきろうロード
第七話で直江が高耶を連れて訪れた場所。また同話ラストシーンで高耶が一人海の向こうに蜃気楼を見ていた場所もここ。
早月川河口から片貝川河口まで、魚津市内の海岸線を南北に走る道路。晴れた日には立山連邦も望め、県内でも有数のドライブコースになっている。毎年しんきろうマラソンなどのロードレースも行われる。
この道沿いには、蜃気楼展望地点、魚津埋没林博物館、魚津港、ほたるいか群遊海面と、魚津の見どころが揃っている。

しんきろうロードから
蜃気楼展望地点を望む
|
蜃気楼展望地点
埋没林博物館横にある蜃気楼観測スポット。
オープニングラストシーンで高耶と直江が立っている場所はここである。
春の蜃気楼
4月~6月の暖かな晴れの日中、北からの微風が吹く日に出現しやすい。
暖かい空気と、海面の冷たい空気の境で、光の屈折が発生。実像の上側に虚像が現れて蜃気楼になる。
冬の蜃気楼
12月~3月。
春とは逆に、実像の下側に虚像が現われる。
気温が海水温より低いときに出現。対岸の風景が伸びたように、水平線から浮いたように見える。
-
魚津の蜃気楼
海の向こうに現れる幻影を、昔から魚津の漁師たちは天上の国の神の城の名である「喜見城」と呼んだ。その他にも、「海市」「蓬来島」「狐の森」「貝櫓」など様々な呼び名を人々から与えられた。元々、この"蜃気楼"という名は、中国の想像上の生物で龍に似た(一説に巨大な蛤とも)「蜃」という生き物が気を吐く時現れる楼閣のことをいう。
晩春から初夏にかけての晴れた風のない午後、うっすらと現れる幻の街が、だんだんと具体的な姿を形成する。この幻影の街は2,3分のこともあれば3時間以上存在する時もある。
発生は極めてきまぐれで、年に何度も現れることもあれば、9年間まったく出現しなかったこともある(この時は高度成長期の公害が原因とも言われた)。
黒部川上流の冷たい雪解け水が富山湾に注ぎ、三陸沖の温かく湿った暖気が富山湾上空に流れ込む。すると、雪解け水で急激に冷やされた海上の空気の密度が非常に大きくなり、逆に、上空は密度が極めて小さくなる。この差が、太陽光を屈折させるレンズの役目を果たし、陸上の風景を海上に出現させるのである。
江戸時代の昔から、蜃気楼は多くの作品に題材として登場してきた。江戸川乱歩の「押し絵と旅する男」の冒頭は殊に秀逸であり一読をお勧めする。
-
<蜃気楼を見る>
とにかくあせらず気長に待つ。
<蜃気楼発生時期>
4月から6月が断然多い。まれに3,7,9,10月に出現することも。
時間は午後が圧倒的に多い。なかでも14~16時に集中している。
<蜃気楼発生の主な条件>
1.東経140~150度、北緯30~45度に移動性高気圧があり、2,3日晴れがつづいている。
2.当日は晴れあるいは薄曇り。
3.無風か微風。風向きは北。
4.最高気温と最低気温の差が大きく、海水温と最高気温の差も大きい。
<蜃気楼発生場所>
魚津市の海岸ほぼ全域。
-
|

|