栃木県の西北端に位置する日光市は、1200年の長き間、山岳信仰の聖地として存在してきました。市域の90%以上は山林や原野で占められ、その地形は非常に起伏に富んでいます。
日光国立公園の中心である那須火山帯に属する火山群と中禅寺湖周辺などの豊かな自然は、イギリスの湖水地方にも例えられ、避暑地として、19世紀末から内外からたくさんの文化人や著名人が訪れました。
また、東照宮、二荒山神社、輪王寺あわせた「二社一寺」は、平成11年12月4日、「日光の社寺」としてユネスコの世界文化遺産に登録されました。
データ:(2002.1月現在)
登録人口 17,639人(男8,500人 女9,139人)
世帯数 6,597世帯(1世帯当たり 2.67人)
総面積 320.98平方km
消費者物価指数 2000年2月 102
<気候>
内陸性気候。夏季は冷涼、冬季は氷点下になることも多い。季節による寒暖の差は激しく、年間での気温差は40℃を超える。
年平均気温 約12℃(奥日光7.2℃)(東京 約16℃)
8月平均気温 24.4℃
1月平均気温 2.0℃
年間降水量 約2405mm(日本平均約1750mm)
<姉妹都市>
姉妹都市 アメリカ パームスプリング市
地名の由来:
日光開山の祖、勝道上人が、男体山を「二荒山」(「補陀洛山」から取ったという)と名付け、そののち、弘法大師空海が「二荒」を音読みにすると「にこう」と読める事から、「日光」と改称したとされる。
◎車で
東京から 首都高速 東北自動車道宇都宮IC経由で日光宇都宮道路 約2時間30分
大阪から 名神高速道、東名自動車道 首都高速 東北自動車道宇都宮IC経由で日光宇都宮道路 約10時間30分
名古屋から 東名自動車道 首都高速 東北自動車道宇都宮IC経由で日光宇都宮道路 約7時間30分
◎電車で
東京から 東武日光線利用で 約2時間
大阪から 新幹線と東武日光線利用で約4時間30分
名古屋から 新幹線と東武日光線利用で約3時間40分
◎日光までの鉄道
JR東日本日光線
東武鉄道日光線
◎飛行機で(羽田空港着)
大阪から 1時間15分
名古屋から 1時間(成田空港着)
北海道から 1時間30分
福岡から 1時間45分
歴史的スポット
家光廟大猷院、天海大僧正の像、日光山、男体山、含満ヶ淵 など
みどころ
東照宮、二荒山神社、輪王寺の「二社一寺」、日光二荒山神社中宮祠、日光田母沢御用邸記念公園 、東京大学大学院理学系研究科附属植物園日光分園、栃木県立日光自然博物館、小杉放菴記念日光美術館、うるし博物館、イタリア大使館別荘記念公園、小杉放菴記念日光美術館など
自然・温泉
中禅寺湖・男体山、戦場ガ原、湯元温泉、中禅寺温泉、霧降高原 など
イベント・伝統行事
輪王寺外山毘沙門天縁日、強飯式、徳川家光公(大猷院殿御袢忌)、日光二荒山神社中宮祠開山祭、神事流鏑馬弓矢渡式・やぶさめ、男体山登拝祭、日光山輪王寺薪能、日光けっこうフェスティバル・秋の花火、日光東照宮百物揃千人行列 など
特産品
・湯波
輪王寺等での仏徒修行のために日光に集まった、僧、修験者の精進料理用として発展。
京都のゆばより厚めでボリュームがあります。
・日光ビール
日光の社寺が世界遺産に登録された際の記念として誕生。
標高2000m級の日光連山の伏流水で醸造。苦味を抑えた喉越しさっぱりの飲みやすいビール。
・しそ巻唐辛子
もともとは修験者が愛用したもの。日光山輪王寺の強飯式において、強飯受者に強いる言葉のなかにも登場。ご飯が進みます。
・日光下駄
神官や僧侶の履物「御免下駄」から発展。日光名物でありながら日光で買えないもの三題の一つ。
・日光彫
東照宮を造替する名匠たちの余技として製作されたのがルーツ。
「ひっかき」という独特の道具を用いた曲線と塗りが特徴です。
材質はトチノキやカツラ、ホオなど。
・日光茶道具
木地師の余技として誕生した民芸品。ロクロ細工による鑑賞用ミニチュア茶道具。
BACKGROUND OF MIRAGE OF BLAZE
~「炎の蜃気楼」に登場する風景~

含満ヶ淵
|
含満ヶ淵 栃木県日光市日光匠町
憾満ヶ淵とも。
栃木県日光市日光植物園の裏に流れる大谷川沿いにある景勝地。
北岸の岩に「憾満」の意の梵字が刻まれており、弘法大師が筆を投げつけて彫ったという伝説が残る。
古くは不動明王信仰の地で、不動明王の真言の最後をとって「カンマンヶ淵」と名付けられた。
第七話に登場。
化け地蔵 栃木県日光市日光匠町
含満ヶ淵南側の散策路沿いに並ぶ石地蔵。慈眼大師(天海僧正)の弟子が彫ったと伝えられている。
往きと帰りで数える度に数が違う事からこう呼ばれている。昔は約100体の地蔵が列をなしていたが、洪水の度に数が減り、今は70体程になっている。
第七話に登場。

霊庇閣
|
霊庇閣 栃木県日光市日光匠町
含満ヶ淵「憾満」梵字の対岸に位置する。現在の建物は昭和48(1973)年に復元されたもの。
晃海僧正が慈雲寺創建のとき建立した護摩壇で、対岸の不動明王の石像に向かって護摩供養がおこなわれた。
第七話に初登場。
第十三話で直江はここから東照宮へ侵入した。
日光東照宮 栃木県日光市山内2301
徳川家康の遺言により創建された家康を祀る社。
社殿は神仏混淆の山王一実神道の理念にのっとり建造された。
現在の形に整えたのは三代将軍徳川家光。
平成11年12月4日、日光東照宮を含む地域が、ユネスコの世界文化遺産に登録された。
第七話に登場。

陽明門
|
陽明門 栃木県日光市山内2301
日光東照宮表参道の奥に構える極彩色の装飾で有名な楼門。
高さ11m、間口7m、奥行4m。
日が暮れるまで見ていても飽きないことから、通称「日暮ノ門」とも。施された彫刻は500余り。12本の柱の渦巻き状の彫刻は「グリ」と呼ばれ、中に一本だけ上下逆さのものがある。これは装飾が完璧すぎるのをさける為に故意に行ったもので、「魔よけの逆柱」と呼ばれる。
日光は、江戸の真北にあり、東照宮は真南-江戸の方角を向いて建立された。よって、この門の真上には不動の星北極星が常に輝いているのである。
第七話に初登場。
唐門 栃木県日光市山内2301
陽明門を潜るとあらわれる四方軒唐破風の門。
第七話に初登場。
屋根上正面・背面に鎮座するのが霊獣
 。 。

この唐門の向こうに本社が
|
東照宮本社 栃木県日光市山内2301
祭神は徳川家康。陽明門、唐門の奥に位置し、本殿、拝殿、石の間からなる権現造り。
第七話において風魔小太郎に盗まれたツツガ鏡はこの本殿の中に安置されていた。

晩秋の華厳滝
|

観瀑台へのエレベーター
|
華厳滝 栃木県日光市中宮祠2479-2
中禅寺湖畔の滝。男体山の噴火による溶岩が古大谷川をせき止めたことで出現し、中禅寺湖の水が流れ落ち大谷川にかかっている。那智滝、袋田滝とともに、日本三名瀑の一つ。高さ99m、幅約7m。滝壺は直径約40m、水深約5m。
※中禅寺湖の最大深度163mは滝壺よりも60メートルほど低い位置となる。
1月から2月にかけては、細い小滝「十二滝」が凍り、華厳滝自体もブルーアイスに彩られ、幻想的な姿を見せてくれる。
専用エレベーターで下りる観瀑台は、第八話で直江が麻衣子を連れて訪れた際、高坂が出現した場所である。
「華厳」の名の由来は、付近にある涅槃、般若、放等、阿含滝とともに、仏典「釈迦の五時経」から。
~巌頭之感~
明治三十六年、東京の一高生、藤村操(18歳)がこの滝から投身自殺した際にミズナラの木に残した「巌頭之感」の影響で、以後ここでの自殺者が続出。同文中の「人生不可解」は流行語にもなった。
「巌頭之感」(全文)
悠々たる哉天壌、遼々たる哉古今、五尺の小躯を以って此大をはからむとす。
ホレーショの哲學竟に何等のオーソリチィーを價するものぞ。萬有の眞相は唯一言にして悉す。曰く「不可解」。我この恨を懐て煩悶終に死を決するに至る。既に巌頭に立つに及んで胸中何等の不安あるなし。始めて知る大なる悲觀は大なる樂觀に一致するを。
|
|

中禅寺湖と男体山
|
中禅寺湖 栃木県日光市中宮祠
奥日光男体山の梺に広がる湖。国内最大の高山湖。面積11.5平方km、周囲25Km、最大深度163m、水面の海抜高度1269m。男体山の噴火によって出て来た堰止湖である。湖水の透明度が高く(透明度8~10m)、真冬でも凍る事がない。貧栄養湖に属し、湖水の環境基準は「AA」。ここで捕れるニジマスは絶品。
浅岡麻衣子の家は湖畔で旅館を経営している。
→日光中禅寺湖QuickTimeVR

カーブごとに「いろは」の文字が。
|
いろは坂 栃木県日光市明知平周辺
日光市街を中禅寺湖へ至る際経由する道。国道120号。一方通行で往復別々に第一(下り専用)、第二(上り専用)の坂がある。急なカーブが延々と続き、カーブごとに「いろは」の文字が表示されている。
ここをいろは坂と呼んだのは、昭和初期のロープウェイのアナウンスが始まり。
昭和29(1954)年第一いろは坂完成。この時のカーブは30か所。昭和40(1965)年上り専用の第二いろは坂完成後、第一のカーブを2か所減らし第一第二あわせて48カーブにし、きちんと「いろは」が入る状態にした。
第八話で浅岡麻衣子の弟慎也が事故にあったのは下りの第一いろは坂のほう。


上:二荒山神社へと続く参道。
9話に登場。
下:境内の御神木(三本杉)
|
二荒山神社 栃木県日光市山内2307
日光東照宮の西に位置する日光最古の建造物。日光二社一寺の一つ。東照宮一ノ鳥居とは上神道、下神道で結ばれる。元和五年(1619年)の創建で、開祖は勝道上人。男体山山頂に奥宮がある。祭神は大巳貴命。その神域は広大で、3,400ヘクタールにも及ぶ。これは伊勢神宮に次ぐ広さで、本社を中心に日光連山の殆どがその範囲に入る。
日光三社権現の一つであったが、明治四年(1871年)の神仏分離令、神仏混淆の禁止により、以後、二荒山神社本社と称する。
神苑に湧く二荒山霊水は、飲むと目の病が癒え、智恵がつき、若返るとされている。酒造りに適しており、「酒の泉」とも。敷地のあずまやで、二荒山霊水を使った抹茶や珈琲などが味わえる。また神苑入り口に立つ灯籠には刀傷が。これは武士が化け物に斬り付けた際についたものとされ、化灯籠と呼ばれている。
浅岡麻衣子の弟慎也が木縛されていたのは御神木(三本杉)の向かって右側の杉。

輪王寺三仏堂
|
輪王寺 栃木県日光市山内2300
日光二社一寺の一つ。天台宗の門跡寺院。天平神護二年(766年)創建。開基は勝道上人。比叡山延暦寺、東叡山寛永寺と並ぶ天台宗三山。
本堂の三仏堂の内陣には、高さ8mを越す木造金箔の座像が安置されている。堂塔の数が多く、本堂付近に15院。
山岳信仰の場として栄えたが、安土桃山時代に小田原の北条氏に加担したことから豊臣秀吉に寺領を没収され一時衰退。後に天海僧正が貫主となり東照宮を創建した後ことから再び勢い盛んになる。「輪王寺」の寺名は、明暦元年(1655年)に守澄法親王が輪王寺宮を称したことを由来とする。
第十二話にて北条氏政がここで護摩修法を行った。



上:八脚門から見上げる。
後ろに男体山が。
中:八脚門と中禅寺湖。
下:八脚門から中禅寺湖を望む。
13話の高耶の目線。
|
二荒山神社中宮祠
栃木県日光市中宮祠2484
日光山内の二荒山神社の中宮で、男体山を背にした中禅寺湖畔に境内がある。
延暦三年(784)、勝道上人が男体山の冬期遙拝所として、ここに二荒山権現を祀ったのがはじまり。男体山を御神体とする山岳信仰の霊場としてにぎわった。中禅寺湖に向かう境内には、中門、唐門、拝殿、本殿と、朱塗りの社殿が並んでおり、いずれも江戸時代に造営され、重文。境内奥、拝殿の脇の登拝門からは、男体山頂にある奥の宮に続く登山道が開かれている。この門は毎年5月5日の開山祭から10月25日の閉山祭までの期間だけ開門される。
第十三話において、氏政は中禅寺湖の湖畔に位置する浜鳥居の前に車を止め、階段上の八脚門の前の高耶と対峙した。
◎交通
中禅寺温泉から湯元行バス3分
二荒山神社前下車
◎駐車場
有(無料)乗用車10台


上:御宝塔
下:右側の門が「鋳抜門」
13話で高耶の操る大ツツガはこの門から入ってきた。
|
東照宮奥社御宝塔
栃木県日光市山内2301
東照宮奥社、東照宮祭神徳川家康の神柩を納めたものである。建立以来、一度も開けられたことがない。創建は元和七年(1621年)。元は木造であったが、後に石造に。それが天和三年(1683年)の地震で破損したため、5代将軍徳川綱吉が現在の唐銅製に再建した。唐銅とは金・銀・銅の合金。作者は椎名伊予。八角型五段の基壇の上に更に三段を唐銅で鋳造し、その上に宝塔をのせている。高さは5メートル。内部は深秘事項とされ、本殿同様、口外する事は許されない。宝塔の前には鶴の蝋燭立て、香炉、花瓶が置かれているが、これらは、朝鮮国王から送られたもの。東回廊の奥社参道入り口には有名な「眠り猫」も。
|

|


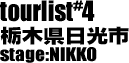







 -唐門の上に立つ
-唐門の上に立つ












